『人間行動論コース創設のころ』 田中二郎先生
田中二郎先生より、人間行動コース設立当時のお話をお寄せ頂きました (平成24年7月)
二郎先生は、現在信州にお住まいで、山スキー、農作業、山登り、犬の散歩などなど毎日忙しく(笑)しておられるそうです。
アップルランドでの同窓会の際に『ブッシュマン、永遠に。』にサインして頂いた方多いと思います。 このたび『ブッシュマン、永遠に。』に3章分の論文を加えて英文出版することになり、7月にその準備がようやく一段落してほっとしてるところだそうです。 「外国での研究はやはり国際語で公刊する必要があります。」とのこと。
◆『ブッシュマン、永遠に。』はアマゾンでも購入できますよ。まだの方はどうぞ!
『人間行動論コース創設のころ』
 1981年のおそらく3月に入ったばかりの頃だったと思う。私らは弘前大学へ来て一体どんなことをしたらいいのだろうか、弘前とはどんなところだろうかと、当時東大理学部人類学研究室の助手をしていた丹野正君と2人で打ち合わせを兼ねて下見に出かけてきたことがある。弘前駅は古い木造の建物で、駅前通りには残雪が路傍に積まれ、凍てついた夕暮れ道に人通りもなく、侘しげであった。えらいところへ赴任してくることになるなあ、と正直思ってしまった記憶がある。
1981年のおそらく3月に入ったばかりの頃だったと思う。私らは弘前大学へ来て一体どんなことをしたらいいのだろうか、弘前とはどんなところだろうかと、当時東大理学部人類学研究室の助手をしていた丹野正君と2人で打ち合わせを兼ねて下見に出かけてきたことがある。弘前駅は古い木造の建物で、駅前通りには残雪が路傍に積まれ、凍てついた夕暮れ道に人通りもなく、侘しげであった。えらいところへ赴任してくることになるなあ、と正直思ってしまった記憶がある。
弘前大学人文学部では、人文学科を従来の哲・史・文の枠を越えて、大幅に改組拡充しようと文部省とも折衝を重ね、その年の4月に新体制で発足する運びとなっていたのである。学部改革の先頭に立っていたのは当然のことながら、当時の学部長、道教研究者の秋月觀暎先生であったが、じつは陰で陰謀をめぐらせ知恵を授けていたのは、学部長と同じく中国(満州族)研究者の細谷良夫先生であった。もう1人この改革推進に欠かせなかった人物がいた。秋月先生より年配で、学部最年長の実力者、哲学、倫理学の伊東洋一先生はお年の割に気が若く、進取の気に満ち満ちておられ、細谷さんの改革案にほれ込んで、秋月先生の決断を迫り、学部の総意をまとめるのにたいへんな力を発揮された。
細谷さんはご出身の東北大学で同期だった友人で東北大で文化人類学を教えている杉山晃一先生に相談をもちかけられた。哲史文をばらして地域ごとに枠を組み直し、 日本文化論、東洋文化論、西洋文化論とそれらの基礎となるものとして人文基礎論の各コースを置く。そして、新しい体制の目玉として考えられたのが、文化人類学を柱とし、社会学や心理学などの関連分野をも包摂した形で人間行動論コースを新設するというものであった。
日本文化論、東洋文化論、西洋文化論とそれらの基礎となるものとして人文基礎論の各コースを置く。そして、新しい体制の目玉として考えられたのが、文化人類学を柱とし、社会学や心理学などの関連分野をも包摂した形で人間行動論コースを新設するというものであった。
具体的な人選の段階になると、杉山さんもさすがに荷が勝ちすぎたか、1人は適任者として教え子で大学院を終えたばかりの池上良正君(文化人類学、宗教学)を推して来られたが、主任教授を始めとするあとの人選については、インド、ネパールのフィールドでの恩師にあたる川喜田二郎先生に相談された。京都大学地理学の出身で当時は筑波大学におられた先生は、登山、探検のベテランでもあり、梅棹忠夫民博館長とは中学時代からの親友で、私にとっても山と探検、そして人類学の大先輩に相当する。霊長類研究所というサル学の本拠地に11年も奉職していた私は、この新研究室の創設というのにおおいに気を引かれ、転職の求めにすぐさま応じることにし、すでに話が決まっていた丹野君(文化人類学、ピグミー研究)と一緒に弘前に来ることになったのである。
4月1日から弘大人間行動論コースに着任したわたしたち3人は、一体何から手をつけてよいのやらまったく五里霧中の道を歩み出した。引っ越し荷物を前に研究室に茫然とたたずんでいた私のところに初めて顔を現したのは2年生に進級してきたばかりの南真木人君だった。彼は山岳部に身を置く長身の山男で、何カ月か前に行動コースができると決定するやそこを進路と決め、2年生になるや早速、京大山岳部でヒマラヤ登山をも経験した私に面会を求めてきたのであった。「僕はもう弘前大学では2年目ですから、ここでは僕の方が先輩ですよ。」開口一番の彼の言い草であった。「そうや、そうや、よろしく頼みまっせ。」やがて始業式が終わって経田、佐々木、三浦、武藤など個性に満ちた1期生が続々と集まってきた。いま手元に人間行動ネットワーク名簿(平成11年7月作成)というのがあるが、それによると1期生は11名、2期生以上は20名から30名の大所帯となってきている。
わたしたち3人がまずやらなければならないのは、1期生を前にして授業や実習をどのように進めていくかという本来の教育方針と同時に、人間行動論コースに認められた教授陣7名のうち残りの4名をいかに補充していくかということであった。授業は各教員の専門分野に合わせて、概論からフィールドワークをもとにした具体的な調査結果などを披歴していくこととしても、実習としては何から取り組んでいったらよいのだろうか。わたしたちはまず、弘前という町、そして津軽という土地を知ることから始めなければならなかった。この地域に住む人びとの行動を知る。ねぷた、ねぶたなくしては弘前や青森の1年はなりたたない、という土地柄を知り、まずは身近な弘前ねぷたを題材にして地域研究の出発点とすることにした。
 教員の補充に関しては、コース設立の条件である文化人類学に加えて、社会学、社会心理学の学徒を加えなければならない。責任者の私自身が40歳という若造であることから、全体に若づくりの体制で行こうと意見がまとまり、広く全国に人材を公募した。そしてあまたの候補の中から厳選していったのが、田中重好(地域社会学、慶応義塾大)、林春男(社会心理学、UCLA)、北村光二(霊長類学、文化人類学、行動学、京都大)今井一郎(文化人類学、京都大)であった。これら4人の選考には1、2年の年月が必要であった。こうして徐々に陣容が整い、ねぷた祭り調査も軌道に乗りかけたところであった。毎週の実習の時間には学生も交えてたっぷり議論の機会があったが、じつは私たち教員連は毎日昼飯時には誘いあって向かいの学食に出向き、小一時間はさまざまなことを話し合った。大半は他愛もない雑談が占めたが、ときに重要な話題がのぼることもあった。行動論コースの教員全員が連日学食の一隅に陣取り会食する姿はよそ眼には異様に思えたらしく、弘前大の話題になったようであるが、我々にとってはチームワークを固め、教育研究の方針を練りあうにもまことに貴重な機会だったのである。
教員の補充に関しては、コース設立の条件である文化人類学に加えて、社会学、社会心理学の学徒を加えなければならない。責任者の私自身が40歳という若造であることから、全体に若づくりの体制で行こうと意見がまとまり、広く全国に人材を公募した。そしてあまたの候補の中から厳選していったのが、田中重好(地域社会学、慶応義塾大)、林春男(社会心理学、UCLA)、北村光二(霊長類学、文化人類学、行動学、京都大)今井一郎(文化人類学、京都大)であった。これら4人の選考には1、2年の年月が必要であった。こうして徐々に陣容が整い、ねぷた祭り調査も軌道に乗りかけたところであった。毎週の実習の時間には学生も交えてたっぷり議論の機会があったが、じつは私たち教員連は毎日昼飯時には誘いあって向かいの学食に出向き、小一時間はさまざまなことを話し合った。大半は他愛もない雑談が占めたが、ときに重要な話題がのぼることもあった。行動論コースの教員全員が連日学食の一隅に陣取り会食する姿はよそ眼には異様に思えたらしく、弘前大の話題になったようであるが、我々にとってはチームワークを固め、教育研究の方針を練りあうにもまことに貴重な機会だったのである。
1983年5月26日正午、秋田沖を震源とする日本海中部大地震を題材にしてこのときの人々の行動を実地に調査しようと言いだしたのは、地震のあった翌日の昼飯時であった。林君が口火を切り、重好君が直ぐそれに同調し、2人の勢いに呑まれた同席の皆も一瞬考えたのち、「いっちょやってみるか!」と、たちまちにして衆議一決。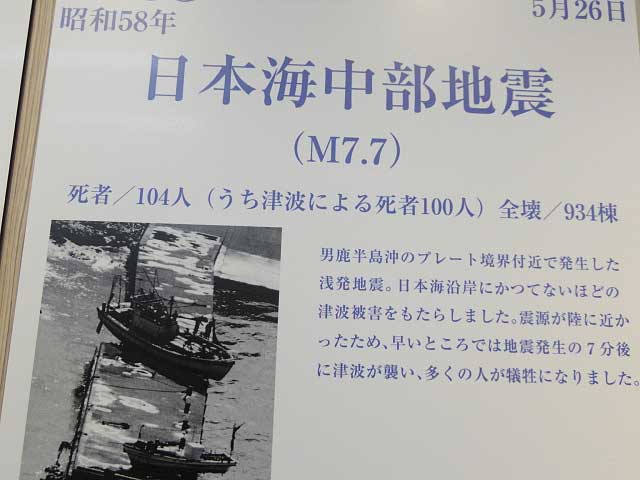 ねぷた調査への準備にかかりつつあった実習は一転して地震・津波災害時の人間行動の研究へと早変わりした。コース内では実習としてこれに取り組むことにしたが、学生を大勢引き連れて津軽半島の先端から遠足の児童100人ほどが津波にさらわれた秋田県男鹿半島までの被災地の各地まで泊まりがけの調査を行うには資金も必要となった。
ねぷた調査への準備にかかりつつあった実習は一転して地震・津波災害時の人間行動の研究へと早変わりした。コース内では実習としてこれに取り組むことにしたが、学生を大勢引き連れて津軽半島の先端から遠足の児童100人ほどが津波にさらわれた秋田県男鹿半島までの被災地の各地まで泊まりがけの調査を行うには資金も必要となった。
秋月学部長を説得して、この調査を全学的な規模で展開し、弘前市および青森県からなんとか調査補助金を獲得してくる工夫を考え抜いた。理学部の地震学、地震火山観測所はもちろんのこと、環境生物学、人文学部内でも経済政策、社会政策、教養部の社会学、教育学部の地理学、地学、医学部の公衆衛生学、法医学、農学部の農地工学、農業造構・施設学、学外からも東北女子大学家政学部の植物学からの参加をえて、総勢26名よりなる弘前大学日本海中部地震研究会を組織することができ、さまざまな資金を捻出することも可能となった。
人間行動コースでは、各教員ごとに指導学生を割り振り、はげしい揺れが起きた時の対応、津波の前兆として海の水が後退したときの村人たちの避難の仕方など、各地各様の事態に合った聞き取りや現地踏査にあたった。翌1984年3月には人間行動論コースが中心となって334ページにおよぶ研究会としての報告書を完成させることができ、この業績に対し、河北新報社から河北文化賞を受賞する栄誉までを受けるにいたった。
地震の研究が一段落して、本格的にねぷた祭りの調査に落ち着いて取り組み直し、本来の津軽研究への探究がこのあとも続けられることになって、人間行動論コースはさらに発展を遂げて行くことになるが、残念ながら私自身は弘大に5年半在任しただけで新設の京都大学アフリカ地域研究センターに転任することになった。短期間の弘前在住ではあったが、季節感あふれ、山とスキー、岩魚釣り、山菜とり、そして学問に没頭できた津軽の地は、生涯忘れがたい思い出の地となりつづけるところであった。
2012年7月21日
安曇野市穂高にて
当時私は、ひたすら津波から避難した皆さんやねぶた小屋で作業する皆さんと話して、見て、記録した。 自分の目で見て感じること。その場の匂いを嗅いで、話して歩いてみないと気が済まない。今でも沁みついている。